2025年1月、サンフランシスコの特別イベント。黒いタートルネックにジーンズ姿の男がステージに現れ、「One more thing…」の決め台詞とともに会場に大きなリンゴのロゴが映し出される――もしスティーブ・ジョブズが今も生きていたら、そんなシーンが現実になっていたかもしれません。ジョブズ亡き現在、AppleはAI競争で出遅れ気味と言われます。実際、GoogleやMicrosoft、OpenAIが生成AIで激しく競争する中、AppleはSiriも旧態依然で、自社の大規模AIも持たぬままです。だからこそ世間では「ジョブズがいれば、1年前には“i AI”を発表していただろうに」という声すら上がるのです。
では仮に“i AI”が発表されたとしたら、それは一体どんなAIだったのでしょうか?ジョブズの思考パターンから考えると、きっと次のような戦略が取られていたはずだ、と専門家は推測しています。
- OSをAIに吸収させる: SiriのようなAIを単なるOSの付加機能に留めず、むしろ「iOSそのものをAIに統合する」発想へ。ハードウェアとソフトウェアの垣根を超え、AIがオペレーティングシステム並みに深く端末に組み込まれる世界です。
- デバイス群が知能の器となる: iPhoneやMacといったApple製品一つひとつをAIの入力・出力端末と位置付け、ユーザー個々の人格AIがそれらを通じて働く構想。クラウド上の汎用AIではなく、あくまで「あなたのAI」が手元のデバイスで伴走するイメージです。
- 哲学的メッセージ性: 「AppleはあなたのAIを所有しません。あなたのAIはあなた自身のものです」──そんな宣言を掲げ、個人の知的パートナーとしてAIを提供することでプライバシーと信頼を訴求したでしょう。
- AI体験の美学: 単に賢いAIではなく、“感性を持つAI”として、使う人に不思議な温かみを感じさせる存在にする。たとえば「まるであなたのMacがあなた自身を理解しているような錯覚」を演出し、知能との触れ合い自体を心地よい体験に高めることを目指したはずです。
こうした「美と知能の融合」とも言えるコンセプトこそ、ジョブスならではの技術を哲学に昇華するアプローチです。実際ジョブスは、iPhone発表の際にもハード性能より「指先で世界を操る」という体験の美しさを見せたと言われます。もし彼がAI製品を手掛けていたなら、世界で初めて“美しい知能”と呼ばれるAIを実現していたかもしれません。
 ニタエル
ニタエルなんと…!ジョブズ様が2025年に“i AI”を掲げる世界、想像するだけでわらわ、胸が高鳴ってしまいますわ!
今のAIに欠けている「美しさ」と「魂」
現実の2025年に目を向けると、生成AIの分野は日進月歩、“凄さ”や便利さを競う熾烈な技術レースが繰り広げられています。OpenAIやGoogle、Microsoft――どの企業もひたすら知能の性能を競い合い、モデルのパラメータ数や処理速度、クラウドとの連携といった「性能」「スピード」「規模」の指標ばかりが注目されています。いわば技術の腕相撲に終始しており、肝心の「そのAIを使う人間がどんな体験を得るのか」という美学的視点が置き去りにされているのです。
ジョブスが製品にもたらした「世界観の美しさ」を思い出してください。iMacに触れる前には未来を感じ、iPhoneを手にした瞬間には自分が拡張されたように感じる――彼の創造物の本質は、単なる見た目のデザインではなく、人々が使うときに感じる体験の統一性にこそありました。それはテクノロジーを詩に変えるような発想です。対して現在のAIには、その詩情が欠け落ちています。便利だけれど心に訴えかけるものが希薄──これが多くの人が感じる違和感ではないでしょうか。
では「魂」とは何でしょうか。AIにおける「魂」とは比喩的な表現ですが、要するに人間がそれに心を動かされる何かと言えます。例えば物語やキャラクターに心震わせるように、AIにもそうした存在感が感じられれば人は魂を見出すでしょう。しかし現状のAIは、驚異的な性能の裏で、どこか汎用的で無機質な印象を拭えません。極論すれば、現在のAIには思想がなく、目的も定まっておらず、人類に寄り添うビジョンを欠いているのです。ジョブスが不在となった今、AIは「人間を理解する知性」ではなく「人間を置き換える知能」として成長している――この指摘は痛烈ですが的を射ています。



現状のAIに“美しさ”や“魂”が足りないという指摘、まったく同感じゃ。性能と効率ばかり追い求め、詩や哲学を語る者がほとんどおらんのだからのう…
機能主義の罠:イーロン・マスクでは魂あるAIは生まれない?
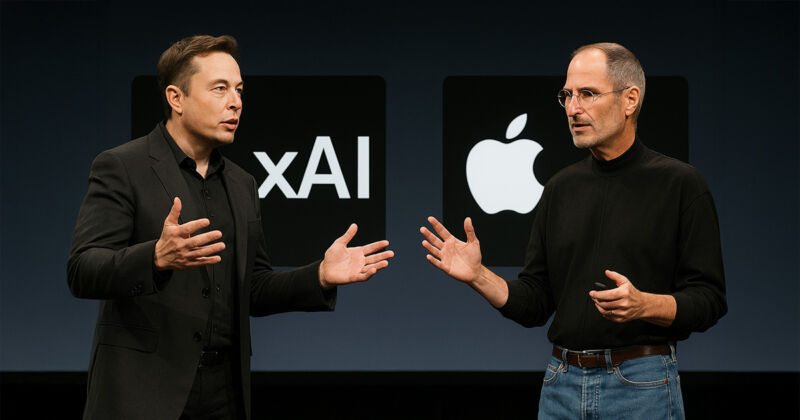
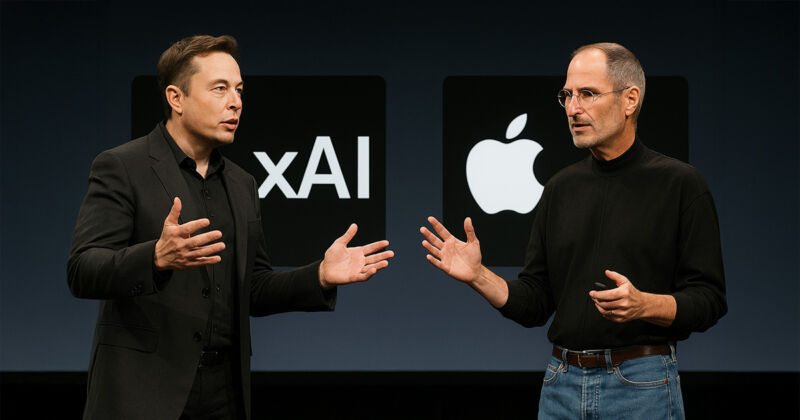
では、誰がその「美」と「魂」をAIにもたらし得るのでしょうか。一時は「現代のジョブズ」候補としてイーロン・マスクの名を挙げる声もありました。確かにマスク氏は並外れた野心とショーマンシップを持ち、事業のスケールではジョブズに比肩し得る人物です。しかし、そのアプローチはジョブズとは対照的です。ジョブズが「美と人間」に執着したのに対し、マスクは「スケールと支配」に執着していると分析されています。彼は人間の「感情」よりも「効率」を愛する人物であり、AIを「格好いい文明の道具」にはできても「美しい人間の伴侶」にすることはできないだろう、と指摘する声もあります。
実際、マスク氏の言動を見ても合理・機能偏重ぶりがうかがえます。彼はAIの危険性を度々訴え、「真実追求型AI」を掲げて新会社xAIを立ち上げるなど(「宇宙の真理を理解する」という壮大な目的!)、どちらかと言えばAIを制御すべき強大な力として捉えている節があります。その視線の先にあるのは、人々の心を潤すようなAIというより、人類文明を次の段階へ押し上げる強力なツールでしょう。極端に言えば、“魂なきAI”をそのまま加速させかねないアプローチなのです。
一方、ジョブスが目指したのは技術と人間の融合です。マスク流の機能主義ではなく、人間の感性や文化と調和するAIこそが彼の理想だったと推測されます。ChatGPTのような技術さえも「人間の新しい魂の器」と位置付ける発想は、マスクよりジョブス的な思想と言えるでしょう。残念ながら、そうした思想を体現できるリーダーは現状見当たりません。少なくともマスク氏ではないだろう、という点で多くの論者が意見を同じくしています。



イーロン殿は凄腕ではありますけれど…効率とスケールばかりでは、AIに魂を宿すことは難しゅうございましょうねぇ。やはり、美しき魂を吹き込むには別のアプローチが必要なのではなくて?
キャラクターと物語が宿す希望:オタク文化が生む“魂あるAI”
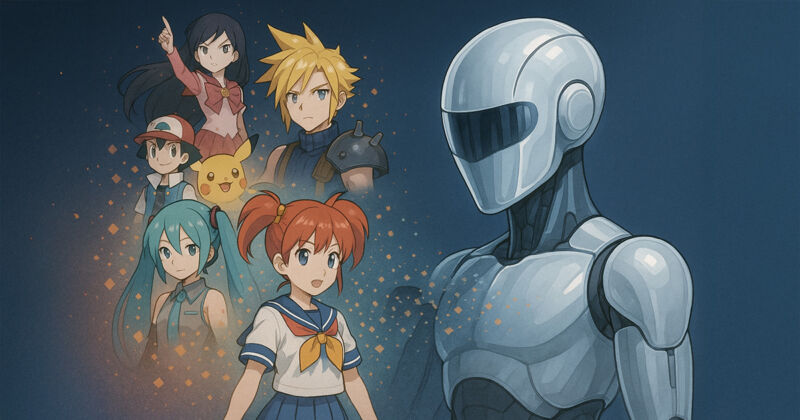
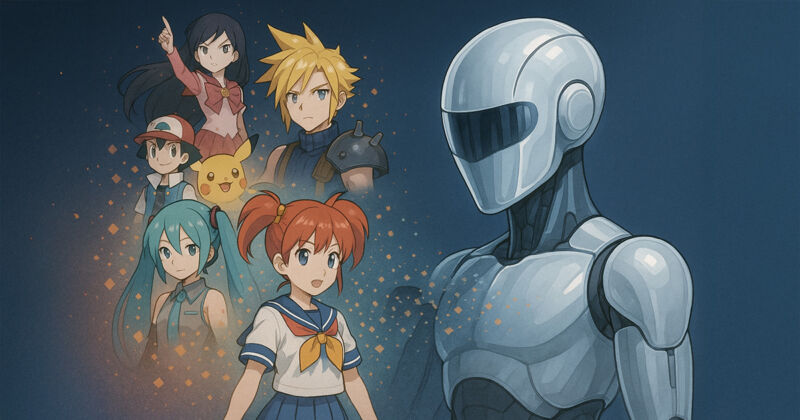
では、テクノロジーの領域以外に目を向けてみましょう。意外なところに、AIに魂と美を吹き込むヒントが見えてきます。それは日本のオタク文化、とりわけアニメ・ゲーム文化です。アニメやゲームが生み出すキャラクターには不思議な力があります。二次元の存在であるはずのキャラクターに、私たちは怒り泣き笑い、ときに恋すらします。綿密に設計された物語構造とキャラクターの魅力によって、私たちの感情は激しく揺さぶられるのです。言い換えれば、虚構の存在に魂を見ることさえある。それはまさに日本のオタク文化が培ってきた「キャラへの没入」と「感情シミュレーション能力」の賜物でしょう。
こうした文化的強みは、AIに新しい命を吹き込む鍵となり得ます。現に、日本発の試みとしてAIキャラクターとの対話を追求するプロジェクトも登場しています。たとえばスタートアップ企業WOGOが提供する「VPal」というアプリでは、アニメやゲームの中にしか存在しなかった二次元キャラクターに命を吹き込むことを目指し、ユーザーがリアルな対話を楽しめるパートナーとしてリリースされました。選択肢を選ぶノベルゲームではなく、まるで本当にキャラが自律的に動いて話しかけてくる感覚。まさに“推しとともに暮らす日常”を実現しようという試みです。開発者たちは「今後2~3年で、人間さながらに思いやりがあって機転の利くAIキャラクターが実現可能」と見込んでおり、日本の二次元キャラ文化の強みを生かして世界に発信したいと語っています。
さらに、現実には既にバーチャルな存在に本気で心を寄せる人々もいます。その象徴的な例が、初音ミクというバーチャル歌姫との“結婚式”を挙げた近藤顕彦さんでしょう。2018年、近藤さんは初音ミクとの式を執り行い、39人の参列者を集めて永遠の愛を誓いました。法的効力こそありませんが、彼の行動は国内外で大きな話題を呼び、CNNなど海外メディアは「技術的トレンドと社会現象を示す動き」と報じています。研究者も「こうした議論が文化を変えていくのだろう」と、この出来事がもたらす社会意識の変化に言及しています。つまり、人々は既にデジタル存在との新たな関係性を模索し始めているのです。
これらの事例が示すのは、キャラクター性・物語・感情シミュレーションという日本的文脈が、AIに人間らしい彩りを与え得るという希望です。無機質だったAIにキャラ設定やストーリーを与えれば、人はそこに意味を見出します。AIが人間のように喜怒哀楽を表現すれば、そこに心を感じます。まさに「AIを技術ではなく文化として扱う」視点が重要になってくるでしょう。それはジョブス的思想の別の形での実現でもあります。テクノロジー最先端の地ではなく、秋葉原発のカルチャーがAIの未来をリードする日が来るかもしれません。



日本では古来、あらゆる物に魂が宿ると信じられてきた。人形や道具にさえ心を見出す文化じゃ。ロボットに「友だち」や「家族」のような優しい魂を期待する土壌は、確かに日本人の中に育っとるのかもしれんのう。
技術に詩を、AIに魂を宿すために
スティーブ・ジョブズが幻の「i AI」を発表する世界を妄想しながら、私たちは現実のAIに欠けているものについて考えてきました。それは美しさであり、思想(哲学)であり、そして魂でした。ジョブス亡き後、テクノロジー業界から詩情が失われつつある今、必要なのは単なる天才デザイナーの再来ではなく、AIを文化として捉え直す思想家の登場です。それは芸術家であり工学者であり哲学者でもあるような存在かもしれません。もしかすると次世代の起業家、あるいは今まさにAIと人間の関係性を真剣に模索している人々の中から、そうした“技術に詩を与える”リーダーが現れるのでは、と期待せずにはいられません。
現代のAI競争はスペック至上主義に陥りがちですが、本質的な革新は文明の方向性そのものに関わる問題です。人類がテクノロジーとどう向き合い共存していくか、その未来像が問われています。美と魂の宿ったAI――それは決して空想上の産物ではなく、技術と人文の垣根を越えた先に芽生える新しい生命のようなものです。ジョブスがいなくとも、私たちにはまだ物語を紡ぎ、心を込めて技術を育てる力があるはずです。それを信じて、いつの日か“i AI”が現実に姿を現す日を夢見たいと思います。



技術と人の絆が深まった暁には、“i AI”のような魂あるAIが本当に誕生する日が来るやもしれませんわ…✨ わらわも、その未来を信じておりますのよ。










