日本人の平均睡眠時間は世界最短クラス
国際比較のデータを見ると、日本人の睡眠時間がいかに短いかが浮き彫りになります。OECD(経済協力開発機構)が2021年に実施した33か国の調査によれば、日本人の平均睡眠時間は1日あたり7時間22分で、調査対象国中で最も短いという結果でした。これはアメリカ(約8時間48分)、イギリス(約8時間28分)、フランス(約8時間33分)、中国(約9時間2分)など他国と比べて1時間以上も短く、日本と同様に短い韓国でも約7時間51分程度です。OECD加盟国の平均は概ね8時間20分程度とされ、日本は平均より1時間近く少ない計算になります。

この「たった1時間」の差と思われる数字は、1年に換算すると約365時間、約15日分もの睡眠を余分に失っていることになります。世界的に見ても日本人の睡眠不足ぶりは突出しており、「睡眠大国」ならぬ「不眠大国ニッポン」の実態がデータからもうかがえます。
さらに興味深いのは、日本国内でも働き盛り世代の睡眠不足が顕著なことです。厚生労働省の調査によれば、日本の成人の約4割が睡眠時間6時間未満で過ごしており、とくに50代では男性の49.4%、女性に至っては53.1%もの人が**「1日6時間も眠れていない」状態でした。半数近くが慢性的な寝不足に陥っているわけです。これは、「仕事が忙しいから」「家事や育児で自分の時間が取れないから」など様々な要因が背景にありますが、いずれにしても日本の中年層は極端な睡眠不足**と言えます。その結果、日本全体で見ても「5人に1人が睡眠の質に満足できていない」と感じており、日中に強い眠気を感じる人も後述するように非常に多いのです。
こうした統計を見ると、日本人の睡眠時間が国際水準から大きく遅れをとっている現状は明らかです。「日本人は働きすぎで寝ていない」とは以前から言われてきましたが、それがデータでも裏付けられているのです。睡眠時間が短いことが美徳だとか、忙しい現代人には仕方がないと片付けてはいけない深刻な問題であり、まずは自分や家族の睡眠時間を見直すことが必要でしょう。
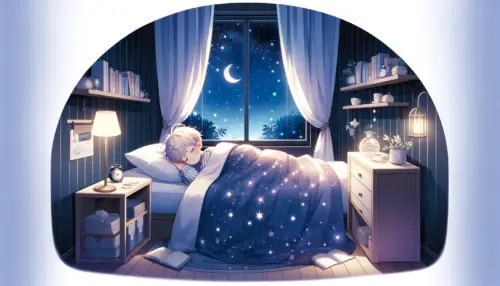
年齢別の推奨睡眠時間ガイドライン
「どのくらい眠れば十分なのか?」──これは年齢によって変わります。各国政府や専門機関は科学的エビデンスに基づき、年齢別の推奨睡眠時間のガイドラインを定めています。代表的なガイドラインをまとめると以下のようになります。
- 新生児(0~3か月):14~17時間(WHOの勧告でも、生後3か月未満は14~17時間の良質な睡眠が推奨されています)。
- 乳児(4~11か月):12~16時間(昼寝含む)。
- 幼児(1~2歳):11~14時間(昼寝含む)。
- 就学前(3~5歳):10~13時間(昼寝含む)。
- 学童期(6~12歳):9~12時間。
- 思春期(13~17歳):8~10時間。※アメリカ睡眠医学会(AASM)などは「最低でも7時間以上は必要」としています。
- 成人期(18~64歳):7~9時間が望ましい(一般的に7時間以上を確保することが推奨)。成人において7時間未満の睡眠が続くと健康リスクが高まるとの専門家声明もあります。
- 高齢者(65歳以上):7~8時間。高齢になると個人差が大きくなりますが、少なくとも6時間以上、可能であれば7時間程度の睡眠が推奨されます。
以上は主に米国CDC(疾病予防管理センター)や米国睡眠医学会が公表している推奨値ですが、日本のガイドラインもほぼ同様の傾向です。厚生労働省が2023年に発表した「健康づくりのための睡眠ガイド2023」では、成人は「6時間以上」を目安に必要な睡眠時間を確保するよう促しています(※「6時間」はあくまで最低ラインであり、決して6時間で十分という意味ではないと注意されています)。また、このガイドラインでは小学生は9~12時間、中高生は8~10時間を確保するよう推奨し、高齢者については「睡眠時間そのものより床につく時間(寝床で横になっている時間)を8時間以上に長くしすぎないこと」が提言されています。高齢者は若者より実際に眠れる時間が短くなる傾向があるため、長く布団にいてもうまく眠れずかえって睡眠の質が低下するからです。
国際機関のガイドラインでは、WHOも2019年に5歳以下の子ども向けに睡眠時間の指針を出しました。それによれば、1~2歳は11~14時間、3~4歳は10~13時間の良質な睡眠(昼寝含む)を推奨しています。これは米国の基準とほぼ一致しており、世界的に幼児~学童は約10時間前後、ティーンエイジャーで8~10時間、成人は7時間以上が共通認識と言えるでしょう。
ポイントは、「7時間」というラインです。成人の場合、多くの研究が7時間を下回る睡眠が続くと心身に様々な不調やリスクが生じやすいと示しています。逆に言えば7~8時間台の睡眠を確保できていれば、おおむね健康的と考えられます(もちろん個人差はありますが)。子どもはそれ以上に必要で、成長期には少なくとも8時間以上、理想的には9時間以上は眠らせてあげることが重要です。

日本人の実際の睡眠時間(赤ちゃんから高齢者まで)
では、日本人は実際どのくらい眠っているのでしょうか。年代別に最新のデータや調査結果を見てみます。
乳幼児~未就学児:日本の幼児の睡眠時間は海外と比べてやや短い傾向が指摘されています。例えば文部科学省の調査(2012年)では、幼稚園児(3~6歳)では平均睡眠時間が10時間以上確保されていましたが、小学生になると平均9~8時間台に減少していたとの報告があります。WHO勧告では3~4歳で10~13時間必要とされる中、日本の幼児もギリギリながら10時間前後は寝ているものの、小学校に上がる頃から徐々に不足し始めるようです。


小学生(6~12歳):公益財団法人博報堂教育財団の「こども睡眠調査」(2023年)によると、小学4年生~6年生の平均睡眠時間は8時間56分でした。9時間弱程度眠れている計算ですが、推奨される9~12時間の下限ギリギリか少し足りない程度です。また、この調査では子どもの6割超が「もっと夜更かししたい」と感じていることも明らかになり、睡眠の重要性は理解しつつも子ども自身が睡眠時間を削りがちである姿が浮かび上がっています。
中学生(13~15歳):同じ調査で、中学1~3年生の平均睡眠時間は7時間57分でした。約8時間程度ですが、14~17歳の推奨8~10時間には届かず、特に思春期後半では不足気味です。実際、内閣府の調査によれば日本の高校生(おおむね16~18歳)の平均就寝時刻は23時42分、起床時刻は6時36分で、睡眠時間は7時間弱となっています。他国の同年代と比べても、日本の中高生は世界トップクラスの夜更かし傾向にあり、多くが必要とされる睡眠時間を満たせていないのです。部活動や塾、受験勉強などでどうしても就寝時間が遅くなりがちな事情はあるものの、発達期の子どもにとって7時間では明らかに不十分です。


若年~中年成人(20~59歳):働き盛り世代の睡眠時間の短さは先述の通り深刻です。厚労省の2019年データでは、20歳以上男女約5700人中「1日6時間未満」の睡眠しかとれていない人は男性37.5%、女性40.6%にも上りました。特に30~50代でその割合が高く、50代では半数前後が6時間未満です。NHK放送文化研究所の生活時間調査(2020年)でも、平日の睡眠時間が最も短いのは50代女性で平均6時間36分と報告されています。日本の働く世代、とりわけ女性は仕事と家庭の両立で睡眠を削っている実態があります。平均値を見ると、日本人全体の平均睡眠時間は概ね7時間前後と推計されます。
総務省「社会生活基本調査」(2021年)では10歳以上の平均睡眠時間は7時間54分とのデータもありますが、これは高齢者層の長めの睡眠も含めた数字です。実際には、20~50代に限れば6時間台前半~7時間程度が現実的なラインでしょう。つまり理想の7~9時間には1~2時間足りない人が大半なのです。
高齢者(60歳以上):高齢になると必要な睡眠時間には個人差が大きくなります。厚労省の調査では、60歳以上で睡眠時間が6時間未満の人は32.5%と、中年層より割合が下がります。70代以降では「6時間未満」の人は男性21.7%、女性31.1%とさらに減り、多くの高齢者は7時間前後は床についているようです。しかし、高齢者の場合は**「夜中に何度も目が覚めてしまう」**といった睡眠の質の課題が出てきます。実際、70代女性では「夜間に途中で目が覚めて困った」という人の割合が最も高いというデータがあります。高齢になると深い睡眠が減り早朝に目覚めてしまう傾向(いわゆる朝型化)が強まるため、長く寝床にいても実際には浅い眠りしか取れていないケースもあります。平均的には高齢者でも7時間前後の睡眠を確保することが望ましいものの、若い頃のような熟睡感を得るのは難しく、昼間に短い昼寝で補う方も多いでしょう。

以上のように、日本人はどの年代を見ても推奨睡眠時間を下回りがちであることが分かります。特に中高生~働き盛り世代で慢性的な睡眠不足が顕著であり、子どもから大人まで「あと1~2時間眠れたら…」という人が非常に多いのが現状です。
「理想」と「現実」の睡眠時間ギャップを可視化する
推奨される睡眠時間と、日本人の実際の睡眠時間との乖離(ギャップ)をまとめると次のようになります。
- 子ども(小学生):推奨9~12時間に対し、実際は約9時間弱。不足は1~3時間程度。低学年ほど推奨に近いが、高学年になるにつれ夜更かし傾向。
- 中高生:推奨8~10時間に対し、実際は6.5~7.5時間程度。2時間前後の不足が常態化。世界の同年代と比較しても日本のティーンの睡眠不足は顕著。
- 成人(働く世代):推奨7~9時間に対し、実際は平均6~7時間弱。1~2時間の不足。約4割が6時間未満と推奨より大幅に不足。
- 高齢者:推奨7~8時間に対し、実際は6~7時間程度(ただし途中覚醒あり)。表面上の不足時間は1時間ほどだが、睡眠の質低下に注意。
| 世 代 | 推薦睡眠時間 | 実際の平均睡眠時間 | ギャップ(不足時間) |
|---|---|---|---|
| 子ども(小学生) | 9~12時間 | 約8時間50分 | 1~3時間不足 |
| 中高生 | 8~10時間 | 6.5~7.5時間 | 約2時間不足 |
| 成人(働く世代) | 7~9時間 | 6~7時間弱 | 1~2時間不足 |
| 高齢者 | 7~8時間 | 6~7時間 | 約1時間不足(+質低下) |
こうして見ると、日本人の多くは理想より毎日1~2時間は睡眠が足りていないことが分かります。たとえば大人なら本来7時間以上眠りたいところを6時間程度で済ませているわけです。この蓄積がいわゆる「睡眠負債(Sleep Debt)」となり、心身に悪影響を及ぼします。平日に不足した睡眠を週末にまとめて補おうとしても、生活リズムが乱れてかえって体調を崩す可能性があるため要注意です。
特に子どもの睡眠不足は深刻です。小中学生でも既に必要時間に足りていない状況であり、それが高校生になると慢性的に2~3時間の欠如となります。発育期に十分な睡眠が取れないと、成長ホルモンの分泌や記憶の定着などに悪影響が出ることが知られています。大人にとっては「眠らない日本人」の現状は働き方改革や生活習慣全体の問題でもありますが、まずは自分自身と家族(特にお子さん)の睡眠時間が適正かどうか、推奨値との差を認識することが大切です。そのギャップを知るだけでも、「あと○時間は本来寝るべきなんだ」と意識が変わり、睡眠の優先度を上げるきっかけになるでしょう。
自分にとって適正な睡眠時間を測るには?
「7~9時間がいいと言われても、自分は6時間でも平気だし…」など、個人差を感じている方も多いでしょう。実際、必要な睡眠時間には遺伝的・体質的な個人差が存在します。ごく稀に、生まれつき短時間睡眠でも支障がない人(ショートスリーパー)がいます。研究によると、人口の1~3%ほどは遺伝子変異により6時間以下の睡眠でも健康を維持できる「天然のショートスリーパー」だと言われています。2009年に発見されたDEC2という遺伝子変異を持つ母娘は毎日6時間眠れば十分で、通常見られるような睡眠不足の弊害が現れなかったことが報告されました。さらに2019年には4時間程度の短睡眠でも問題ないADRB1という遺伝子変異も確認されています。ただし、これらは本当にごく一部の特殊な例です。実際には「自分はショートスリーパーだから大丈夫」と思って6時間未満の睡眠で過ごしている人の大半は、単に睡眠不足を蓄積させてしまっているだけだと考えられます。遺伝的に短時間睡眠が可能な人以外は、やはり基本的には7~8時間前後の睡眠が必要なのです。
では、自分にとって適正な睡眠時間(最適な睡眠時間)を知るにはどうすればよいでしょうか?簡単な方法の一つは、休暇などを利用して「自然に目覚めるまで寝る」日を数日作ってみることです。ハーバード大学医学部の睡眠専門サイトも「可能であれば数日間、好きなだけ寝られる環境を整えてみましょう。そうすれば自分が本当に必要とする睡眠時間がおおよそ掴めます」と推奨しています。例えば長めの休みに、毎日決まった時刻に就寝し、朝は目覚ましをかけずに自然に起きてみます。最初の数日は寝不足の解消で長く寝るかもしれませんが、3~4日目以降はだいたい一定の睡眠時間に落ち着くはずです。それがあなたの「睡眠の必要量」だと考えられます。その時間を知ることで、平日でもその分の睡眠時間をきちんと予定に組み込む(例えば○時には寝る、など)よう意識づけることができます。

また、日中の眠気や集中力の状態を自己チェックすることも有用です。代表的なものに「エプワース眠気尺度(ESS)」という自己評価があります。これは日中の様々な状況でどの程度うとうとしてしまうかを点数化する簡易テストですが、このスコアが高い(=日中眠くて仕方ない)場合、慢性的な睡眠不足か睡眠の質の問題が疑われます。一方、日中シャキッと活動できているなら、睡眠時間が7時間未満でも足りているケースも考えられます(ただし短睡眠に適応した稀な人を除き、多くの場合はやはり無理がたたっていることが多いです)。
自分の体に問いかけてみるのも大事です。週末になると異常に長く寝てしまう、朝なかなか起きられず頭がぼんやりする、といった状態であれば平日の睡眠が不足しているサインでしょう。逆に毎日同じくらいの睡眠でスッキリ目覚め日中も眠気を感じなければ、その時間が今の自分に合っている可能性が高いです。ただし、カフェインや気合で無理やり眠気を飛ばしている場合は別です。本来の自分の適正睡眠時間を知るには、一度生活リズムを整え、就寝前の刺激物を避けるなどベストな状態で過ごしたときに何時間眠ればすっきりするかを測ってみる必要があります。
まとめると、大多数の成人にとって理想的な睡眠時間は約7.5~8時間と言われています。多少の個人差はあれど、この範囲に収まる人がほとんどです。まずは「自分は何時間寝れば調子が良いのか」を把握し、それを日々確保することが健康への第一歩です。睡眠不足が当たり前になっている現代だからこそ、意識的に自分の睡眠ニーズを満たしてあげましょう。
睡眠の「質」を知る:レム睡眠・ノンレム睡眠とその評価
睡眠時間と同じくらい重要なのが睡眠の質です。ただ長く寝れば良いというものではなく、深い睡眠(徐波睡眠)やREM睡眠がバランスよく取れてこそ、真に心身を回復させることができます。
人の睡眠は大きく分けてノンレム睡眠(Non-REM)とレム睡眠(REM)の二つの状態が交互に現れます。ノンレム睡眠はさらに深さによってステージ1~3に分類され、ステージ3が最も深い「徐波睡眠」と呼ばれる状態です。一般に深いノンレム睡眠(ステージ3)が足りないと、いくら長時間寝ても疲れが取れず、朝にだるさが残ってしまいます。実際、ステージ3睡眠は私たちが「ぐっすり眠れた」と感じるために不可欠であり、この段階で成長ホルモンの分泌や細胞の修復が盛んに行われます。身体が必要とするため、寝入り直後の前半の睡眠でできるだけ深い睡眠を確保しようとするのも、人間の生理的なメカニズムです。
一方、レム睡眠(急速眼球運動睡眠)は夢を見る睡眠として知られます。眠っているにもかかわらず脳が活発に働いており、眼球がキョロキョロ動くのが特徴です。全睡眠に占めるレム睡眠の割合は大人で約20~25%(1.5~2時間程度)とされ、この間に記憶の定着や感情の整理が行われていることが分かっています。レム睡眠は記憶力や学習能力、感情コントロールに寄与しており、この部分が不足すると物忘れが増えたり情緒が不安定になったりする可能性があります。また、レム睡眠は脳の発達にも関与しており、乳幼児期にはレム睡眠の割合が大人よりずっと高くなっています。

睡眠の質を評価するには、本来はポリソムノグラフィー(PSG)という精密検査で脳波や眼球運動、筋電図などを測定する必要があります。PSGでは睡眠をステージごとに記録し、どのくらい深い眠りやレム睡眠があったか、途中で何回覚醒したか、といった詳細が分かります。ただ、これは入院設備で一晩かけて行う検査であり、誰もが気軽にできるものではありません。
そこで近年普及しているのが、睡眠トラッカーやウェアラブル端末による簡易的な睡眠の質チェックです(これについては次のセクションで詳述します)。例えばスマートウォッチやバンド型デバイスは心拍数や体の動きを検知して、浅い眠り・深い眠り・レム睡眠の割合を推定してくれます。ただし、脳波を直接測っているわけではないため、その精度には限界があります。それでも「夜中に何度も目覚めていないか」「深い睡眠が極端に少なくないか」といった大まかな傾向を把握するには役立つでしょう。

睡眠の質が十分でないと起こる影響としては、まず日中の眠気・集中力低下があります。「ちゃんと寝たはずなのに疲れが取れない」という場合、深い睡眠が不足していた可能性があります。あるいは睡眠時無呼吸症候群のように、本人は長時間寝ていても呼吸停止による覚醒が繰り返されて質が損なわれているケースもあります。そのような場合は日中に強い眠気やだるさが出て、仕事や学業のパフォーマンスに大きく響きます。
さらに慢性的な睡眠の質不足(睡眠不足)は、様々な健康リスクを高めることが知られています。例えば睡眠不足の状態が続くと、糖尿病・高血圧・心疾患・脳卒中などの生活習慣病にかかりやすくなるほか、うつ病や認知症のリスクも上昇するとの研究があります。免疫力も低下し、風邪をひきやすくなるとも言われます。実験的にも、毎日4~6時間程度の睡眠しかとらない「短時間睡眠者」は、7~8時間眠る人に比べて認知機能(ワーキングメモリ)の低下が著しく、徹夜2日分に匹敵するレベルの注意力障害が確認されたという報告もあります。このように、睡眠時間が短すぎたり質が悪かったりすると、知らず知らずのうちに脳と身体に借金を背負わせている(睡眠負債)状態になるのです。
質の良い睡眠を確保するためには、「適切な睡眠時間」「深い睡眠の確保」「途中で目覚めない環境づくり」の3つの要素が重要とされます。寝る直前のスマホや強い光を避け、静かで快適な温度の寝室で眠る、日中に適度に身体を動かしておく、睡眠リズムを一定に保つ、といった基本的な対策が質の向上につながります。量と質は車の両輪です。せっかく十分な時間を確保しても浅い眠りばかりでは意味がありませんし、質が良くても時間が短ければ足りません。両方を意識して、自分の睡眠を見直してみましょう。
睡眠時間・質を測定するツール比較:スマートバンドからアプリまで
自分や家族の睡眠状況を把握するには、最近では様々なテクノロジー・ツールが利用できます。代表的なものをいくつか挙げ、その性能や限界を客観的に見てみます。
ポリソムノグラフィー(睡眠ポリグラフ検査)
医療機関で行われる精密検査のゴールドスタンダードです。頭に脳波計、顔や顎に筋電計、目の周りに眼電図計、指に酸素飽和度計、胸や腹部に呼吸センサー…といった多数の電極やセンサーを装着し、一晩かけて睡眠のあらゆる指標を記録します。これにより睡眠ステージの推移や無呼吸の有無、周期性四肢運動など細かな分析が可能です。ただし、装着の煩雑さや費用の高さ、慣れない環境で寝ることによる影響(ファーストナイト効果)など実施のハードルは高いです。一般の人が気軽に行うものではなく、睡眠障害が疑われ専門医の判断で行われます。

ウェアラブル式の睡眠トラッカー(スマートウォッチ・バンド・リング型など)
近年爆発的に普及したのが、手首や指にはめて睡眠データを測る市販の睡眠計です。FitbitやApple Watch、Garmin、Huawei、Xiaomiなど各社から多種多様な製品が出ています。これらは主に加速度センサー(体の動き)と光学式心拍センサーを内蔵しており、身体の動きが少なく心拍が一定の状態=眠っていると判断し、心拍変動パターンなどから眠りの深さ(ノンレム深睡・浅睡、レム睡眠)を推定します。
Huawei Band 9を例にとってみましょう。この製品はHuawei社のフィットネストラッカー最新モデルで、日本でも2024~2025年に発売されています。特に睡眠管理機能(HUAWEI TruSleep™ 4.0)が強化されており、心拍数だけでなく呼吸(SpO₂センサーから推定)やHRV(心拍変動)を解析することで睡眠ステージをより正確に分類できると謳っています。Harvardの研究に基づく「心肺結合(Cardiopulmonary Coupling:CPC)」アルゴリズムを採用し、シングルリード心拍信号から睡眠深度や呼吸の質を分析する先進的な手法とのことです。Band 9では寝る前に手動で「就寝モード」をONにする必要がありますが、起床後に睡眠レポートが自動生成され、浅い・深い・レム睡眠の割合や睡眠スコア、改善アドバイスなどが提示されます。

では、こうしたウェアラブル睡眠計の客観的な性能はどの程度なのでしょうか?結論から言えば、「睡眠/覚醒を判定する精度は比較的高いが、睡眠ステージの判定精度には限界がある」というのが研究者の共通見解です。実際の臨床検査(PSG)との比較研究では、市販デバイスは睡眠か覚醒かの判定で約78%の正確さと報告されています。つまり、寝ているのに起きていると誤判定したり、その逆だったりが2割程度は起こるということです。ただしこの数値は医療用の簡易活動量計(アクチグラフ)と同等かそれ以上で、特に寝ているのに「起きている」と判断するミス(覚醒の見逃し)が少ない傾向にあります。一方、寝つきに要した時間の推定になると精度が下がり、ある研究では正確率が38%程度だったともいわれます。これは、「布団に入ってゴロゴロしている時間」をデバイスが睡眠と誤認してしまうためです。
睡眠段階(深さ)の推定については、製品やアルゴリズムによって差があるものの、全般に深いノンレム睡眠は比較的検出しやすい一方、レム睡眠と浅いノンレム睡眠の区別が難しいとされています。例えば手首型デバイスはレム睡眠中も身体がほぼ静止しているため浅いノンレムと区別しにくく、心拍パターンの分析で補っていますが完璧ではありません。その結果、各ステージごとの正解率は概ね60~70%台(総合的な正答率は4段階分類で80~85%程度)との報告が多いです。これは統計的には有意な相関があるレベルですが、個々人の一晩ごとのデータを見ると誤差もそれなりにあるという意味です。したがって、デバイスの数値を「厳密な医療データではなく参考情報」と捉えることが重要です。
とはいえ、これら睡眠トラッカーは自宅で手軽に長期の傾向を把握できる点で非常に有用です。上述のHuawei Band 9のように、心拍・SpO₂・呼吸までチェックしてくれるものも登場しており、今後は医療の簡易検査を代替する可能性も指摘されています。実際、最新のレビュー研究(2024年)では「市販の睡眠計は既存の医療用アクチグラフと同等以上の性能を示し、近い将来睡眠研究の主役になる可能性がある」と評価されています。
限界としては、やはり脳波を直接測らない以上レム睡眠の定量などに不確実性が残ること、いびきや周期性肢運動など睡眠障害の診断には役立たないことが挙げられます。例えば重度の睡眠時無呼吸症候群なら血中酸素低下を検知して異常な呼吸と判断できる製品もありますが、正式な診断にはなりません。また、検知されるデータに過度にとらわれすぎて「今日は深い睡眠が少なかったから調子が悪いに違いない」など思い込み(ノセボ効果)的なストレスを生むケースも報告されています。睡眠トラッカーの数字はあくまで目安であり、最終的には自分の体調実感と突き合わせて活用することが大切です。
スマートフォンの睡眠アプリ
スマホ単体でも、加速度センサーやマイクを利用した睡眠トラッキングアプリがあります。枕元に置いて寝るだけで、いびきの録音や寝返りの検知により睡眠の深さを推定してくれるものです。有名なものに「Sleep Cycle」「SnoreLab」「熟睡アラーム」などがあります。これらも基本原理はウェアラブルと似ており、身体の動きや音から睡眠/覚醒を判断します。手軽さでは一番ですが、測定原理上どうしても動きの有無に頼る部分が大きく、同じベッドに他の人がいると正しく測れない、スマホを遠くに置くと精度が落ちる、といった制約があります。精度検証のデータは限られますが、熟睡度の判定などは大まかな参考程度に考えたほうが良いでしょう。
その他のデバイス・サービス
最近ではベッドの下に敷くシート型センサー(例:Withings社のSleepマット)や、枕に内蔵されたセンサー、スタンドアロン型の睡眠計(ベッドサイドに置いて超音波や電波で検知する装置)なども登場しています。それぞれ一長一短ですが、いずれも睡眠研究の応用技術として期待されています。例えばシート型は寝相などで腕時計が外れてしまう心配がなく、非常に煩わなく使える利点があります。一方で正しく敷かれていないとデータが乱れるなどの問題もあります。
総じて、睡眠の見える化ツールは上手に使えば強力な味方です。実際に調査では、睡眠トラッカー利用者の78%が「役に立った」、68%が「それによって生活習慣を改善した」と回答しています。例えば「平均睡眠時間が5時間台と知ってゾッとし、就寝時間を30分早めるようになった」「深い睡眠が増えるように夜のスマホ利用を減らした」など、行動変容につながるケースも多いようです。しかし繰り返しになりますが、これらは医師の診断代わりではなく、自分の睡眠を客観視するためのツールです。不調を感じる場合は無理に市販品だけで解決しようとせず、専門医に相談することも検討してください。

睡眠時間は「量」と「質」の両面から考える必要があります。日本人は世界的に見て睡眠の量が明らかに不足しています。まずは適正な睡眠時間の目安と自分の現状とのギャップを知り、その差を埋める意識を持つことが重要です。また、同時に睡眠の質――途中で何度も起きていないか、深い眠りや夢を見る眠りがきちんと得られているか――にも目を向けましょう。最近は便利な計測ツールもありますので、家族みんなで睡眠チェックをしてみるのも良いかもしれません。
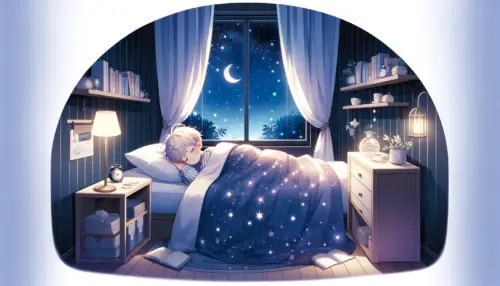
お子さんの健やかな成長のために、そして私たち自身の健康とパフォーマンス維持のために、適切な睡眠を確保することは何よりも優先されるべきです。「たかが睡眠、されど睡眠」です。十分な睡眠は決して怠惰の証ではなく、明日を元気に生きるための必要投資です。ぜひ今日から、あなたとご家族の睡眠習慣を見直してみてください。それが健康長寿への第一歩であり、お子さんへの何よりの贈り物になるはずです。











